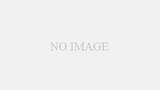節分といって最初にイメージするものにはいろいろあると思いますが、豆や鬼というイメージが強いのではないでしょうか?
節分には豆まきをして、鬼を払ったりしますからね?
家庭でもそうですし、夜のお店でそういうイベントを体験した!って楽しそうなSNSの投稿も見たことがあります。
それにしても、そもそもなんで節分といえば鬼!なんでしょう?
鬼というと、鬼滅の刃で鬼が嫌いなものとして”藤の花”がありましたが、節分で鬼が嫌いなものっていうと他に何があるんでしょうね。
節分に鬼が登場する理由とは?
そもそも、なんで節分といえば鬼が登場するんでしょう?
節分特有の問題みたいなのがあったりするんでしょうかね?
節分と鬼の関係とは
節分で鬼が登場するのには、日本の古来の信仰や風習が深く関わっているようです。
日本では昔から、人々に害を及ぼす邪悪な存在や災いを「鬼」という姿で語り継いできたりしたみたいです。
時代によって扱われ方なども様々のようですが、鬼は災害や疫病、厄などの象徴として捉えられることが多いようで、特に冬から春に季節が変わる節分の時期に、そのような厄災が起こりやすいと考えられていたみたいです。
節分は、一年の始まりとされる立春の前日に行われる行事。そのため、季節の変わり目に生じやすい邪気を払い、新しい年を平穏に迎えるための大切な儀式とされているようです。
古くから中国の陰陽道の思想が日本に取り入れられ、鬼払いの儀式が発展したことが、現代の節分行事のルーツらしいですよ。
この行事では、人々が豆を撒いたり柊鰯を飾ることで邪気を払うだけでなく、厄年の人々が災いを鬼に託して追い払うという意味も含まれているようです。
節分で鬼が嫌いなものには何がある?
節分といえば、豆ですが、豆以外で節分の鬼が嫌いなものって何があるんでしょうね。
調べてみると、けっこういろんなものがあるみたいです。
柊(ひいらぎ)と鰯(いわし)
節分の時期に「柊鰯(ひいらぎいわし)」を玄関先に飾る風習がある地域もあるそうです。
柊の枝と焼いた鰯の頭を組み合わせたもので、これには鬼を遠ざける魔除けの意味が込められているとか。
柊の枝は、葉に鋭い棘がありますよね。そのトゲが鬼の目を刺すと言われているんだそうです。
また、柊って常緑樹なんだそうで、生命力を象徴としてもかんがえられていて、そういったこともあり邪気を払うと考えられたりもしているとか。
それでは、焼いた鰯の頭は何なの?ってことなんですが、焼いたイワシの頭は独特の強い臭いがあって、それが鬼にとって不快であるとされているそうです。
なので、焼いたイワシの頭を家の前に飾っておくことで、お見が家の中に入るのを防ぐ効果があると信じられているようです。
塩も鬼に効き目?
塩って、お葬式のときにも家に入る前に体にまいたり、お清めでお店の前に置塩したりする日本の文化ありますよね。
塩は、古くから浄化や邪気を払う力があるとされるため、節分でも鬼を追い払う際に使用する地域もあるそうです。
豆まきとともに塩を撒くことで、鬼を家の外に追い出すだけでなく、その後の場を清めることができるというわけですね。
音(太鼓や鐘)も鬼は嫌い?
太鼓や鐘などの大きな音は鬼を遠ざけるための手段として用いられていたそうです。
鬼は大きな音を恐れるとされ、音による威圧感がその効果を発揮するんだとか。
なんとなく、熊よけとかそういうのに似てるのかもしれませんね。
確かに、節分の豆まき行事などでは、大きな太鼓を叩いたり鐘を鳴らすこともあったりします。
たんなる儀式上の演出?くらいにしか思っていなかったのですが、どうやら音の力で邪気を払うという意味が込められているらしいです。
きっと、節分のときの豆まきで「鬼は外、福は内」という掛け声もそういう意味合いが含まれているのでしょうね。
音そのものが場の雰囲気を一新し、家族や地域に明るい気分をもたらす効果もあるため、鬼を払うのはもちろん、節分の賑やかさを楽しむこともできますね。
節分は豆まきだけではなく、多くの風習や伝統によって成り立っています。
柊鰯や塩、音、地域独特の食品、掛け声など、それぞれが持つ意味を理解することで、節分の行事により深い意義を感じることもできますね。
これらの知識を活用しながら、鬼を寄せ付けない工夫を取り入れ、家族とともに福を招き入れる節分を楽しんでみると、自分の住んでいる地域の歴史や文化などに触れることにもつながるりそうですね。